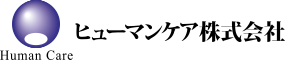- Q
遺言書・遺言は必要?
- A
多くの人は、“死”は遠い先のこととして他人事のように生きている。
そこに盲点がある。
人は死期がわからないから精一杯生きていけるのだが、同時にそれは油断ももたらす。
ヒューマンケアは、日々、人の死に接している中で培ってきた死生観や実務経験にもとづいて、遺言書を残すことの重要性と必要性を訴えている。
遺言書はどこに置く?

遺品整理は、当社の主たるサービスの一つ。
それをすすめる中で、「どこかに遺言書があるかも」「正式な遺言書でなくても、遺志がわかるようなものがあれば取り分けてほしい」といった要望を受けることがある。
もちろん、要望に応えるため、できるかぎりの手を尽くす。
幸い、その類のものが見つかる場合もあれば、残念ながら見つからない場合もある。
そういったものを遺していない場合は仕方がないが、せっかく遺言書(遺志)を遺して逝っても、遺族の手に渡らなければ元も子もない。
そんなすれ違いは、是非とも避けたいものである。
遺言書とは?

民法が求める一定の様式に準じて作成された書面、及びその内容を遺言といい、一般的には、その書面を「遺言書」と言う。
自分の遺志を伝えるものであり法的効力が認められる反面、要件や方式が法律によって厳格に定められている。
したがって、その内容は自由というわけにはいかず、場合によっては残された人の権利を過剰に抑制したり拘束したりすることがあるため、どんな内容でも認められるというわけではない。
遺書とは?

遺言書と似た概念に遺書があるが、これは遺言書より広義に解釈する。
「遺書」と聞くと「亡くなる間際に書くもの」といったイメージを抱いたり、悲観的な局面を想像する向きが多かったりするが、本来は、時期や形式内容に縛られることなく自由に書いてよいものである。
紙に書かれる場合だけでなく、録画・録音や口頭・メール、またはPCデータで残すケースもあるかもしれない。
どのような内容を、どのようなツールを使って残すかは、人それぞれ、その人次第である。
遺言できる内容は?

遺言できる内容は民法で定められている。
遺言事項は大きく4つに分類でき、更に14の項目に分けられている。
「相続財産に関する事項」として、遺産の分割方法の指定・遺産の分割禁止、共同相続人の相続分の指定、相続財産の担保責任、推定相続人の排除・排除の取り消し、特別受益の持ち戻し免除、遺留分侵害請求の負担割合、
「財産処分に関する事項」として、包括遺贈・特別遺贈、生命保険金の受取人変更、一般社団法人・財団法人を設立する意思表示、信託の設定、
「身分に関する事項」として、認知、未成年後見人・未成年後見監督人の指定、
「遺言執行に関する事項」として、遺言執行者の指定、祭祀主宰者の指定が、それぞれ法定されている。
遺言書の種類は?

遺言書は、民法で定められている種類と形式にしたがって作成されていないと法的効力が認められない。
いくつかの方式が定められている中で、実際は普通方式での遺言である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」3方式のいずれかで作られることが多い
その他、特別方式での遺言、具体的には、遭難した船上や負傷で死が迫っている時などの「危急時遺言」、伝染病のため隔離された場所などでの「隔絶地遺言」が認められることもあるが、それにも証人や形式など一定の規定がある。
自筆証書遺言とは?

「自筆証書遺言」は、遺言者が自ら書き、日付・氏名を自筆し押印して作成するので費用がかからず手軽に作成できる。
反面、加筆や訂正などについてはルールが厳しく定められている。
また、家庭裁判所の検認手続が必要で、細かな不備によって無効になってしまうリスクが高い方式でもある。
公正証書遺言とは?
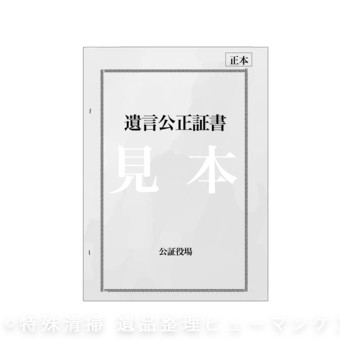
「公正証書遺言」は、遺言者が2名以上の公証人に遺言内容を口述し、それを公証人が筆記し署名・捺印して作成する。
遺言の案を弁護士・司法書士・行政書士などの専門家が作成し、公証人に認証してもらうケースもある。
専門家が作成するので形式的・内容的な不備が生じず、家庭裁判所の検認手続も不要。
公証役場で保管されるので紛失の心配もないが、公証人が2名以上必要になることや相応の費用がかかることが難点。
法的効力の限界は?

「自分の財産は自分が自由に処分してよい」というのが法律の大原則。
したがって、原則として、遺産をどのように使うかについても自由に決めてよいことになっている。
その手段として遺言制度があるわけだが、その制度にも限界はある。
その主な事由は、「遺留分」「公序良俗違反」「詐欺・脅迫・錯誤による遺言」「遺言能力がない状態での遺言」である。
遺留分とは?

遺留分とは、配偶者や子などの近親者に認められる最低限の遺産を取得できる権利。
本来なら遺言が優先されるべきところ、遺族の権利や生活を保障する観点から、最低限、相続されるべき遺産の割合が遺留分として定められている。
この権利は遺言によっても奪うことはできないが、権利を行使するかどうかは相続人次第となり、当然、放棄することもできる。
公序良俗に違反するときは?
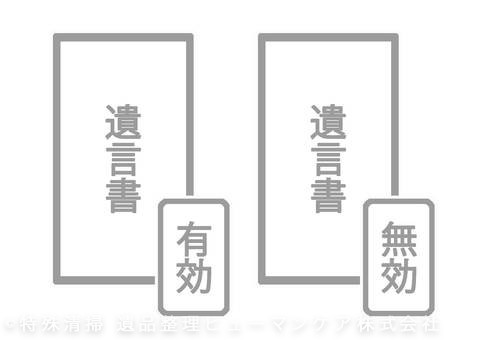
公序良俗に違反する遺言は無効となる。
いくら遺言者の遺志が尊重されるべきであっても、それが公序良俗に反する場合には法的効力は認められない。
ただ、現実には、明らかに公序良俗に違反すると判断できる事例よりも、人と人との関係性や精神性に起因する事例の方が多く、違反の有無については、遺言者や相続人に与える影響などの諸事情を考慮のうえ判断される。
詐欺・脅迫・錯誤による遺言は?

遺言が詐欺や脅迫によってつくられた場合は本人の意思とは言えず取り消すことができる。
また、錯誤による場合は無効となる。
ただし、遺言者が亡くなった後になって立証することは極めて困難なため、実際に取り消しや無効を主張するのは難しいとされる。
遺言能力がない状態での遺言は?

遺言能力がない状態でつくられた場合は無効となる。
ただ、個人の能力(脳力)や精神性に踏み込んだ領域であるため、民法上、遺言能力について明確な定義はなく、抽象的に表現されることが多い。
代表例としては、近年増えつつある認知症があるが、その程度や態様は様々なので、認知症だからといって当然に無効になるわけではない。
遺言者の年齢・病状・精神状態を考慮した心身の状況、遺言時やその前後の言動、遺言者と相続人との関係性、遺言の内容など、遺言能力の有無については諸々の事情を総合的に勘案して判断される。
遺言書のすすめ

遺志を伝えるものにはエンディングノート(終活ノート)もあるが、これには法的効力がなく、そのため、遺産の分配(相続)など具体的な希望がある場合には遺言書をつくっておく必要がある。
自分に合った遺言書を選択し、法的効力を持つ書き方を学び、不安なら弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談してみるのもよいだろう。
余生を充実させるためにも自分で進めることが大切だが、主体性を失わなければ専門家に依頼した方が確実かもしれない。
ヒューマンケアの遺言事例

問い合わせてきたのは70代の女性。
夫や子供はなし。
両親は既に他界し、唯一の近しい血縁者であった弟も先逝。
血縁者としては甥姪がいたが縁は薄く、女性を被相続人とする相続権もなく、事実上、身寄りのない身の上だった。
住まいは賃貸マンション。
かつては一等地に家を所有し暮らしていたのだが身軽になるため売却し賃貸物件に転居。
他にも不動産を保有していたが、何かのときにスムーズに売却できるよう不動産会社と契約し手筈を整えていた。
女性は相応の資産を有しているようで、色々と話を聞いていると経済的に余裕があることが伺えた。
血縁者であっても甥姪に遺留分侵害額請求権はないうえ、もともと他人同然のため女性は甥姪に遺産を相続させるつもりはなし。
葬儀(直葬)・遺骨(散骨)・遺品整理・遺産管理・賃貸自宅の原状回復等々、後始末にかかる費用を差し引いて残った分は何かと世話になった医療機関に寄付することに。
由緒ある事務所の弁護士を遺言執行者とし、その遺志を記載した公正証書遺言を作成していた。
女性は、当社ブログ「特殊清掃 戦う男たち」の愛読者で、「遺品整理や特殊清掃は、是非、ヒューマンケアにやってほしい!」と熱望。
その縁があって、女性の終活に関わることに。
当方は、一度の現地調査と複数回のやりとりを経て、遺言執行者である弁護士に遺品整理等の見積書兼作業概要書を提出。
あとは、“あとは女性が亡くなってから・・・”という、切なくも避けられない現実を待つしかなく、一連の業務はそこで仮終了となったのだった。