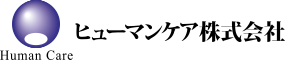- Q
事故物件の賃料は?
- A
ヒューマンケアは、特殊清掃の始祖企業として、数多くの事故物件を取り扱ってきている。
その中には賃貸物件も多く、ほとんどは原状回復を実現し、新たな居住者を募集した。
その際に課題になるのが、新たな賃料。
それは、単なる孤独死なのか、はたまた自殺なのか、また、汚損の程度や補償の有無によっても変わる。
当社は、不動産取引に臨場する中で貯えた多くの実例をもとに、偏りのないアドバイスを行っている。
事故物件は賃貸に供せる?

老朽物件や空室の多い物件で原状回復に莫大な費用がかかる場合、新たに賃貸することを諦めるオーナーは少なくない。
しかし、大半のオーナーは、事故物件であっても原状回復させて新たに賃貸に供す。
原則としてだが、どんなに深刻な汚損でも原状を回復させることは可能。
ただ、特殊清掃・消臭消毒はもちろん、内装工事においても高い専門性が求められるので、一般の工事会社ではなく、当社のような特別汚損の処理に精通した専門会社に任せるのが無難である。
告知義務と賃料設定の関係は?

宅地建物取引法第35条では「賃貸物件を貸す場合、借主に対して必ず物件の詳細を告知しなければならない」と定められている。
したがって、事故物件を貸す場合、貸主は借主に対してその事実を告知しなければならない。
後々、風評などで発覚した場合、大きなトラブルになる可能性が高いので、告知義務の履行は貸主のためでもある。
一方、この法律では賃料についての言及は一切なく、そこからは、事故物件であっても賃料を下げる義務までは負わないことが読み取れる。
事故物件であることを正確に伝えれば、貸主は賃料をいくらに設定しても問題ないのである。
一般的な賃料設定の方法は?

一般的な賃料は、建物の品質や設備、間取り、地域環境など、不動産の鑑定評価によって設定する。
代表的な手法は「積算法」「賃貸事例比較法」「収益分析法」の三種類。
主にアパート・マンション・一戸建などの居住用不動産に用いられるのが、投資コスト・諸経費・期待利益を勘案して算出する「積算法」と、地域相場と物件の強み弱みを勘案して算出する「賃貸事例比較法」。
事業収益を勘案して算出する「収益分析法」は、主にオフィス・店舗など、事業用不動産に用いられる。
賃料設定の具体的手法は?
軸となる手法は「賃貸事例比較法」。
建物構造・築年数・立地条件・目的用途が似た同地域他物件の情報を収集。
近年では、礼金・敷金ゼロの物件も多くなってきているので、その辺のところや空室状況もチェック。
その上で、他物件と自物件を比べ、優れている点と劣っている点をピックアップ。
駅近、浅築(新築)、広面積、高利便設備、重量鉄骨構造、高層階(エレベーターあり)、良眺望、好環境(騒音・治安・店舗など)はプラス材料になるが、その逆はマイナス材料になる。
また、年度末や年末が近づく時期は賃借需要が高まり、賃料を高めに設定しても成約しやすい傾向にあるので、時期に合わせて変動させてもよいと思われる。
賃料設定の注意点は?

余程の問題物件でないかぎり、賃料は安ければ安いほど成約率は上がり、空室リスクは低減する。
しかし、賃貸経営を安定的に行うには、ある程度の収益が必要。
高すぎれば空室が埋まらず、安すぎれば経営効率が下がる。
また、賃料が低くても礼金・敷金・管理費が成約の邪魔になることがあるので、その点も留意。
満室を維持した賃貸経営を実現させるには、“相場観”と“利回り”の両面から検討して収支計算することがポイントとなる。
第三者の意見は必要?

人が亡くなった部屋でも、気にしない人、気にならない人は一定数いる。
ただ、そういった人達でも、賃料が地域相場と同等では一般物件を選ぶ。
事故物件は、割安で借りることができるから ある程度のニーズがあるわけで、その相場観が大切。
貸主一人では視野が狭くなりがちで、賃料をほとんど下げなかったり、逆に下げ過ぎたりするので、相場に精通した不動産会社からアドバイスを受け、多くの他事例を参考にしながら慎重に検討することが大切である。
事故物件の賃料は割安?

「事故物件は賃料を下げなければならない」といった法律上のルールはない。
しかし、事故物件には、一般物件にはない瑕疵があるため、空室を埋めるために賃料は下げざるを得ないのが実状であり通例でもある。
世の中には、「割安でお得」と考え、あえて事故物件を求める人もいるそうで、また、それを紹介する専門サイトもあるよう。
それら一定のニーズに応えて空室を回避するためにも、賃料の低減は避けられない模様である。
事故物件の賃料相場は?

一般的には「2割から3割の減額が多い」とされているが、自然死なのか自殺なのか、事故なのか事件なのか、汚損の程度、復旧の度合い、それらによって変わってくる。
やはり、自然死より自殺、事故より事件、重汚損、小工事の方が減額幅は大きくなる。
とにかく、自由市場(受給バランス)で価格が形成されることが大前提。
賃貸人(売り手)と賃借人(買い手)、双方の必要性が合致するところが着地点(価格)となる。
どちらにしろ、借主にはメリットがあっても貸主にとっては損をするばかりのデメリットでしかない。
ちなみに、当社は数えきれない程の事故物件に携わってきているが、賃料が上がった物件には未だ出会ったことがない(後記事例のような従前維持はある)。
賃料を下げる理由は?

賃料を下げざるを得ない理由は大きく三つ。
一つ目は「心理的瑕疵」。
故人の霊がそこに留まっているような気がしたりして、一般の物件では抱かない恐怖心や嫌悪感が、どうしてもつきまとってしまう。
二つ目は「物理的瑕疵」。
リフォームや清掃が済んでいても、何となく不衛生さを感じてしまう。
リフォームが部分的だと尚更で、一般物件にはない不安を抱いてしまいやすい。
三つめは「認知度の向上」。
各種メディアやSNS、事故物件をまとめた専門サイト、事故物件に暮らすYouTuberや芸能人を通じて“事故物件は賃料が安い”というイメージが世の中に広く定着してきており、それによって“賃料減額は貸主の義務”のような風潮が生まれている。
それらの瑕疵を補いニーズに応えるもっとも簡単な手法が賃料の減額なのである。
家賃補償は?

借主側(遺族等)に一定金額を将来一定期間補償してもらえれば、その分賃料を減額しても損害はない(少ない)。
ただ、事故物件で借主側にその後の家賃補償を求めるかどうかは貸主の裁量によるところであり、そこに法的拘束力はない。
損害を賠償させることは当然の権利のように思われるが、賃貸借契約の法的性格はそう単純なものではない。
貸主vs借主側、裁判沙汰になってしまうようなケースも散見される中、貸主が勝ちきれなかったり、求める程の補償が得られなかったりすることが多いよう。
傷口を広げるリスクもあるため、裁判を考える場合は過去の判例を充分に吟味し、その上で慎重に進めることが大切である。
ちなみに、当社の経験上では、貸主側と借主側の協議により、借主側が従前の賃料の二割を二年間補償するケースが多いように感じている。
売却した方がいいケースもある?
事故物件で赤字経営に陥った場合は、売却も視野に入れた方がよい場合がある。
経営を回復させるには賃料を上げるしかないのだが、賃料を上げるための正当事由を見つけるのは至難。
一般物件でも同様なのに、マイナス材料の多い事故物件では尚更。
そのうえ、賃貸経営を続けていくかぎりは固定資産税・維持管理費などもかかり続ける。
損切りするには勇気が必要かもしれないが、大火傷を負ってからでは遅いのである。
ヒューマンケアの賃料設定事例

現場は、商業地が間近にある住宅地に建つ2DKの老朽アパート。
そこで暮らしていた高齢男性が孤独死。
発見が遅れたうえ暑い時季でもあり、遺体は腐敗。
故人が倒れていた床を中心に汚染は広がり、相応の異臭も発生していた。


当社は、特殊清掃・家財残置物撤去・消臭消毒、そして、内装改修工事を施工。
大家から「内装改修工事は必要最小限で」との要望があり、工事費用を抑えるため、老朽劣化が著しくても簡易修繕やクリーニングでしのげる建具や設備は極力残して再利用。
従前の家賃で貸した場合、一年で回収できるくらいの金額に収めることができた。
「事故物件は家賃を下げなければならない」といった決まりはない。
ただ、下げざるを得ないのが通例なので、てっきり当方もそうなるものと予想。
が、管理会社は「家賃は今まで通りで減額はしない」「このアパートの家賃はもともと安くて人気物件だから」「内装もきれいになったから、次の入居者はすぐに決まるはず」と楽観的。
当然、事故物件であることは告知するはずだったが、地域での経験が豊富な管理会社が言うことだから信憑性は高く、不慮の死をとげた故人の想いを察すると、その結論には何とも言えない安堵感を覚えたのだった。